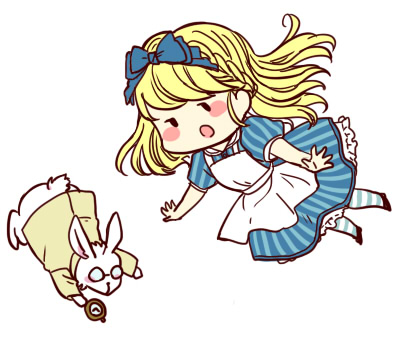『Pina/ピナ・バウシュ 踊り続けるいのち』は、本当に「いのち」と「踊る」ということが繋がって感じられる映画です。
ストーリーよりも何よりも、繰り広げられるダンスに、目が回るような心地にすらなります。
迫りくる音楽と、もたれあい引きずられる男女は、踊っているのか生きているのかすらわからなくなってしまうパワーを持っています。
■目次
ピナ・バウシュは、ドイツの振付家
「天才」と呼ばれました。
68歳でその人生を終えたピナが、なぜ「天才」なのかなんて、この映画をみて思う人は一人もいないはずです。
彼女の振付けたものを踊るヴッパタール舞踏団の動きはあまりのも圧倒的で、言葉を失わせるものなのです。[/voice]
あえて言葉で説明するなら、ピナの振付けたダンスは…
曲線と直線の動きが絡み合い動き続けるといったものです。
曲線がまず、人体の範囲ではない
ダンサーたちの身体が異様に柔らかい…ということではないのです。
[voice icon=”https://ballet-ambre.com/wp-content/uploads/2017/09/kohaku.jpg” name=”いろは” type=”l icon_yellow”]1人のダンサーが片方の腕でゆっくりと円を描くときに、その円がそのダンサーの腕を超えてもっともっと広がっていくように見えるのです。[/voice]たった1人のダンサーが腕を回しただけなのに、その空間がそのダンサーのものとなって、見る者が飲み込まれていくような感覚。
3Dで展開されたこの映画は、3Dでなくとも立体感は感じられました。
そしてぐっとその曲線の中に見る者を引き込んでからの直線。
さっと下ろされた腕が、見る者の感情移入を拒むのです。
見るものの薄っぺらな理解を許さない
コンテンポラリーダンスや、モダンダンスといったものにカテゴライズされるダンスは、創った人の感情が込められていて、それを想像したり自分の勝手な感情を移入させることが容易かったりします。
でも、ピナの振付けるダンスは、浅薄な感情移入や安い「理解」を許さないのです。
ピナという人物も、容易に自分の中へと踏み込むことを許さない人
鋭い眼光と練習室でタバコを吸う姿はカッコいい!
でもダンサーたちにとっては、近寄りがたい存在であろうことは見ている者にもひしひしと伝わってきます。
ピナの中にあるのは「踊る」ということへの情熱とダンサーたちへの愛情
厳しい指導や異常なまでの要求に、やや狂気すら感じてしまうのですが、自分をさらけだして踊るダンサーたちにむける目つきは優しくてはっとさせられました。
自分をさらけ出して踊ることの難しさ
自分をさらけ出すというのは、言葉でいうのは簡単ですが本当は、大人にできることではありません。
しかも「さらけ出して踊る」なんて、「踊っている時点でありのままの自分じゃない」という壁にぶつからなければならないのです。
バレエやダンスをしたことのある人ならきっとわかるはず。
こう見られたい、上手になりたいという気持ちをもって丁寧に踊ることはできるけど、さらけだしたら踊れたもんじゃないんです!
そもそもさらけ出したくて踊っているんじゃなくて、普段の自分じゃない自分になりたくて踊っているんだから…とか思ってしまいそう。
でもピナの振付なら、自分をさらけ出しながら新しい自分に出会えるかも…という気もしました。
ドキュメンタリー映画なので、ストーリーを楽しむという楽しみ方はできない
でも要所要所に挟まれるヴッパタール舞踏団のダンサーたちのインタビューからは、彼らがいかにピナを信頼し、ピナに心酔していたかが分かります。
淡々と語る彼らの口調が、淡白なものであればあるほどに、余計に彼らのピナに対する情熱が感じられました。
言葉ではないんだなという単純でしょうもない感想を抱かずにはいられないほどに、彼らの目つきや動きの方が雄弁です。
音楽もかなりエモーショナル
うっとり聞けるというよりは、心をひっかきまわされるような音楽ばかり。
ずっと緊張感をもって見てしまう、そんな映画でした。
まとめ
映画を貫通している色彩感覚はピナのものではなく、監督のものだということですが、この映画の監督であるヴェンダースがピナと親友だったということに納得のいく色彩でした。
ふいに差し込まれる赤い衣装や、色とりどりの衣装が目くるめくシーンはダンスだけでなくその色彩にも心を撃ちぬかれます。
そして、きっと踊りたくなるはず。
ピナやヴッパタール舞踏団のダンサーたちのようには踊れなくても、「生きている」ことを確認するために。